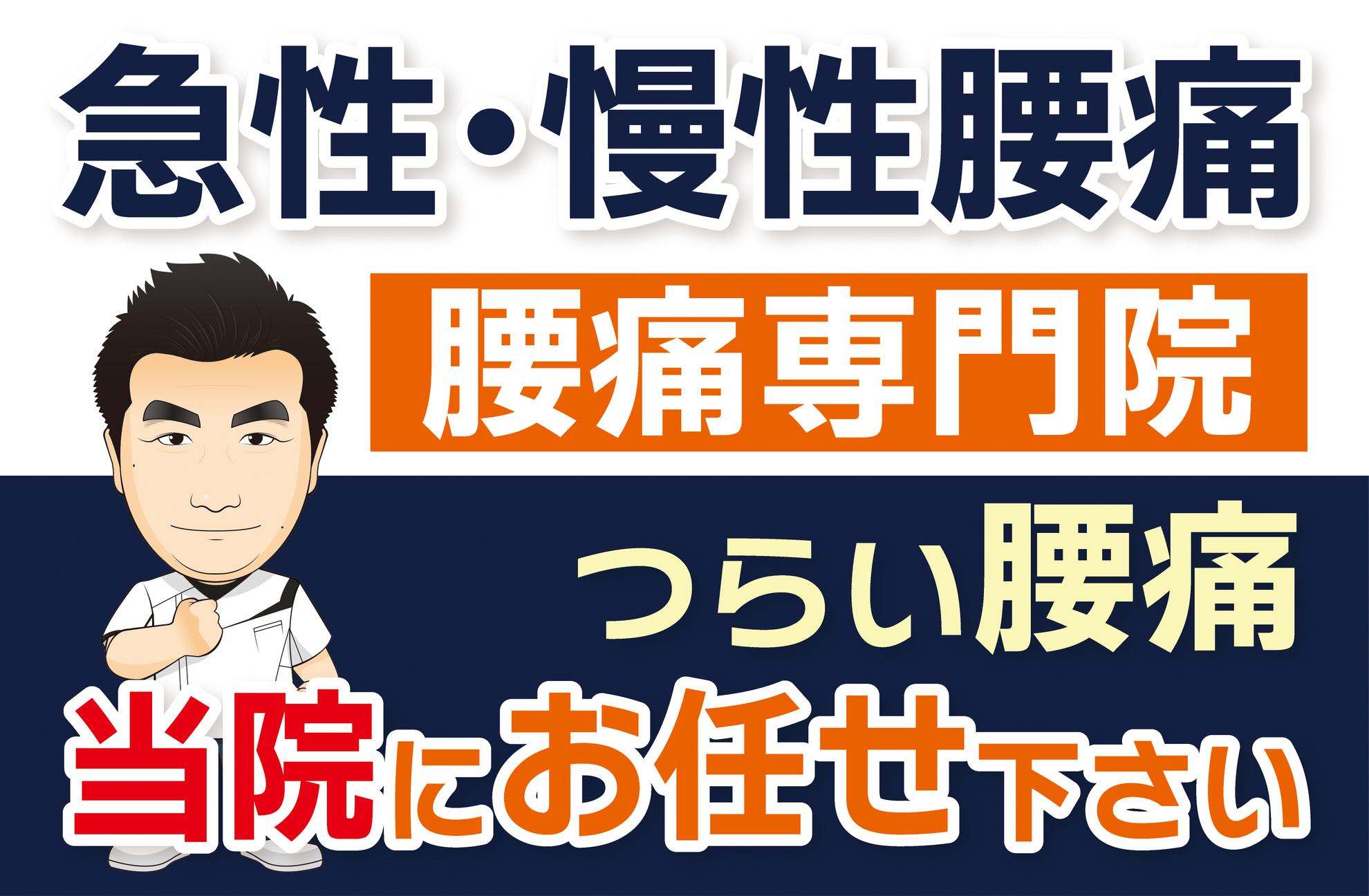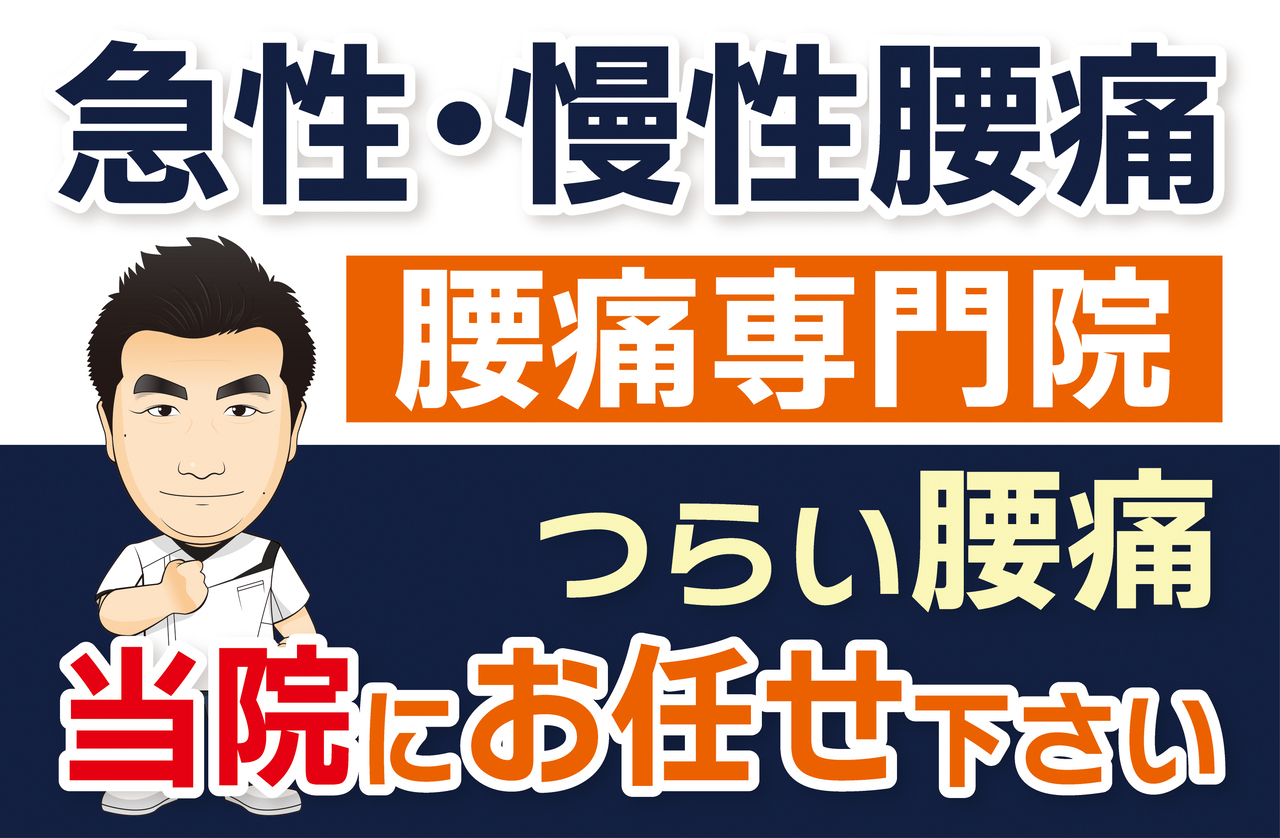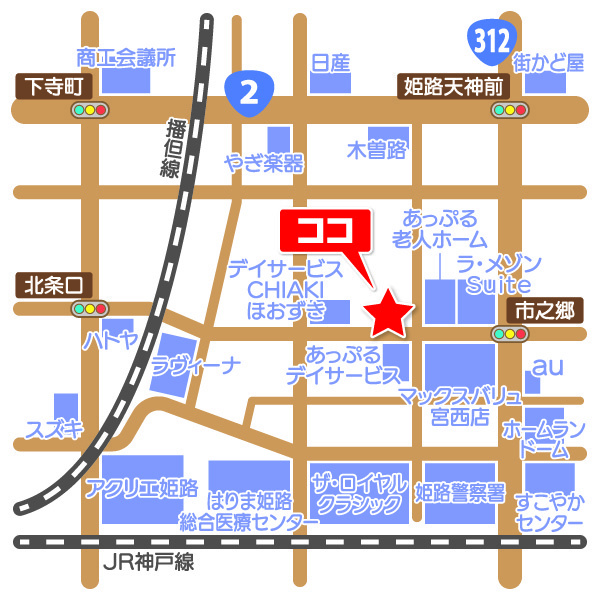足の構造の基礎知識
下腿には脛骨と腓骨という二本の骨があり、内側にある脛骨は末梢の足関節の内側の内果とよばれる骨の突起、いわゆる内くるぶしを形成しています。また外側にある外果はそとくるぶしを形成しています。
そして、足関節は脛骨と腓骨の末梢が形つくるアーチの中に、足根骨のひとつである距骨が入り込む関節の形になっていて、その関節が体全体の荷重を支えている内果と外果では、外果のほうが長く、外側方向に距骨がひねられる力をうけても、外果の骨がそれをブロックしてくれます。
しかし、内果のほうが短いために内側方向への骨のブロックをする力は弱く、足関節を捻挫するときには、外側よりも内側に捻りやすい構造になっています。
また、内果と外果と、距骨、踵骨との間はじん帯でつながっていて、外側のじん帯には前方の前距腓靭帯、中下方の踵腓靭帯、後方の後距腓靭帯という3つのじん帯があります。
さらに内側には幅広く強い、三角靱帯と呼ばれるじん帯が存在します。
足関節、足の指のけがの中で一番多いのが前距腓靭帯や踵腓靭帯の損傷、いわゆる捻挫です。運動量が増加すると起こる腱鞘炎や筋膜炎も多くみられます。オーバーユースによる痛みが出やすいのは足関節や足の指です。